
「妊娠〇ヵ月」「妊娠〇週〇日」など妊娠期間の数え方について、間違えやすく少しややこしく感じる妊婦さんも少なくありません。妊娠経過や赤ちゃんの成長を知るためにも、妊娠期間の数え方を知っておくとよいでしょう。
本記事では妊娠から出産までの平均期間の数え方や体の変化、出産までに準備しておいた方がよいことについてわかりやすく解説します。
出産予定日は、基本的には最終月経の初日から数えます。最終月経の初日を妊娠のスタート(0日目)と考え、280日を経過した40週0日が出産予定日です。まずは、妊娠期間の数え方について詳しく紹介します。
標準的な妊娠期間は280日(40週0日)です。これは、月経周期が28日であることを基準にしています。月経不順の場合や、最終月経の初日を覚えていない場合には、エコーで赤ちゃんの大きさを確認して妊娠週数(予定日)を決めていきます。
標準的な妊娠期間が280日と決められている一方で、予定日ぴったりに生まれる赤ちゃんはとても少ないのが現状です。
正期産(赤ちゃんと妊婦さんに適している出産期間)の時期は、妊娠37週0日~41週6日の35日間です。正期産の割合は、出産全体の約90%と言われているため、出産予定日を過ぎても妊婦さんと赤ちゃんが元気であれば心配ありません。
出産予定日は目安ととらえて、出産やその後の育児の準備を整えていくようにしましょう。
人工授精・体外受精による妊娠では、採卵日や胚移植日を妊娠2週0日と数えます。具体的には以下のとおりです。
| 自然妊娠 | 人工授精・体外受精 | |
|---|---|---|
| 妊娠を数え始める日 | 最終月経の初日が妊娠0週目1日目 | 採卵日または胚移植をした日が妊娠2週0日目 |
| 出産予定日 | 280日後 | 266日後 |
多くの医療機関で用いられている妊娠週数の数え方は、最終月経の初日を妊娠0週1日として、7日間を1つのサイクルとして週単位で数える方法です。月経後胎齢(げっけいごたいれい)ともいいます。
他には、受精後胎齢(じゅせいごたいれい)という数え方もあります。この方法は受精した日を妊娠0週1日とする考え方です。しかし、排卵日や受精日がわからないと、正確な妊娠週数や出産予定日の計算ができないため、あまり一般的には使われていない計算方法です。
ネーゲレ概算法とは、特定の数字を最終月経の月日に差し引きすることで出産予定日が計算できる方法です。具体的には以下の計算式が用いられます。
【出産月】
【出産日】
ネーゲレ概算法は、最終月経の初日が分かり、月経周期が28日の方には簡単に出産予定日が算出出来る方法です。しかし、月経周期が短い人や長い人、不規則な人にはズレが生じます。正確な出産予定日は医師に確認しましょう。
月経周期には個人差がありますが、一般的には28日と言われています。出産予定日は、最終月経の初日から数えて280日(40週0日)としており、月経が28日周期であることがベースになっています。
しかし、月経周期が不安定な場合は、正確な妊娠期間や出産予定日の計算ができないわけではありません。産婦人科でエコー検査を行い、赤ちゃんの大きさや成長の具合から妊娠週数と出産予定日を決めます。
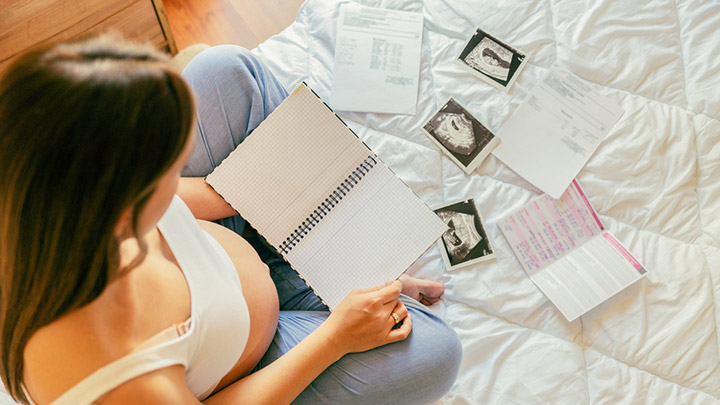
妊娠すると体にはさまざまな変化がおこります。ただし知識を持っておくことで、不安や悩みの少ない妊娠期間を送れるでしょう。ここからは妊娠成立から出産までの妊婦さんと赤ちゃんの体の変化について、妊娠初期・中期・後期の3つにわけて解説します。ぜひ、参考にしてください。
妊娠初期は、受精卵が着床する直前の生理開始日から15週6日までの期間で、妊娠1ヵ月~4ヵ月までの4ヵ月間をさしています。
受精卵が子宮に着床し妊娠が成立した直後は、赤ちゃんは胎芽(たいが)と呼ばれる状態です。胎芽の時期にあったエラやしっぽは、妊娠8週目を過ぎると消失して手足が伸び、顔のパーツが完成します。妊娠12週をすぎると赤ちゃんの骨や筋肉が発達し人間としての身体機能が備わってきます。
妊婦さんは妊娠を維持するために、エストロゲンやプロゲステロン、ヒト絨毛性ゴナドトロピンなどの女性ホルモンの分泌が活発になります。ホルモンバランスが大きく変化し、つわりや気持ちのゆらぎ、眠気やだるさを自覚するようになります。
妊娠初期についてもっと詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
妊娠中期は妊娠16週0日~27週6日の期間で、妊娠5ヵ月~7ヵ月までの3ヵ月間をさしています。一般的には安定期と呼ばれる時期です。
妊娠15週ごろに胎盤が完成すると赤ちゃんは大きく成長し、お腹の中で活発に動くようになります。胎動を感じ始めたり、お腹が目立つようになったりするのもこの時期の特徴です。
つわりが落ち着いてくる妊婦さんも多く、女性ホルモンのバランスも安定し、心身共に穏やかに過ごせる時期でもあります。しかし、個人差も大きく、つわりや肌荒れ、貧血などのマイナートラブルに悩まされる妊婦さんもいます。
妊娠中期についてもっと詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
妊娠後期は妊娠28週0日~39週6日の期間で、妊娠8ヵ月~10ヵ月までの3ヵ月間をさしています。
妊娠8ヵ月になると赤ちゃんはさらに大きくなり、妊婦さんはお腹が前にせり出すため足元が見えづらくなってきます。足のむくみやお腹の張りが気になる妊婦さんが増える時期です。
妊娠9ヵ月になると大きくなった子宮が胃や心臓、肺などの内臓を圧迫しやすくなります。食事をしてもすぐにお腹がいっぱいになったり、胸がムカムカしたりするので、1回に食べる量を減らして複数回に分けて食べるようにしましょう。心臓や肺を圧迫すると息切れや胸のドキドキ、膀胱を圧迫すると尿が近くなるなどの症状を自覚します。
妊娠10ヵ月は赤ちゃんが少しずつ骨盤の中に下りてくるため、胃や肺、心臓の圧迫感が減ってくる時期です。赤ちゃんは3kg前後、身長は50cm程度に大きくなっています。37週0日以降はいつ生まれてきても大丈夫な時期です。出産に向けておしるしや、前駆陣痛などの症状を自覚する方もいます。

赤ちゃんを迎える準備は、妊娠中から始まります。スムーズに出産を迎えるために、行っておくとよいことを4つ紹介します。
母子健康手帳は、妊婦さんと赤ちゃんの妊娠から乳幼児期までの情報を管理する手帳です。妊婦健診や乳幼児健康診査、保健指導や予防接種記録、子育ての情報がまとめられています。
母子保健法第15条では、妊娠した人は速やかに市町村長に妊娠を届け出て、母子健康手帳を受け取ると規定されています。母子健康手帳の受け取りには妊娠届の提出が必要なため、あらかじめ記入してから持っていくとスムーズです。
母子健康手帳は、赤ちゃんの心拍を確認してから妊娠11週までの時期に、市町村の役所や保健センターに受け取りに行くようにしましょう。
母子健康手帳の交付に必要な書類は、妊娠届以外に本人確認書類(免許証やパスポートなど)、マイナンバーカード(個人番号)など自治体によって異なります。事前に確認するようにしましょう。
出産や産前産後に関する休業や給付金について確認しておきましょう。確認しておく項目は以下のとおりです。
出産直前になって焦ってしまわないよう、取得条件や申請期限などを事前に確認しておくようにしましょう。
出産する施設は、大学病院、総合病院、産院、クリニック、助産院などいろいろと種類があります。それぞれの施設によって特色も違うので、選ぶのに迷うこともあるでしょう。
人気の病院や産院では、妊娠初期には分娩予約が埋まってしまうケースもあります。また、「分娩予約の時期は〇ヵ月までに」と決まっていることもあるため、できるだけ早くご自身に合った出産施設を選ぶようにしましょう。
病院や産院選びは、次のような基準で選ぶとよいでしょう。
妊娠の経過や妊婦さんの希望によって選ぶ基準は変わります。パートナーや家族とも相談しながら、妊婦さんが産前から産後までを安心安全、快適で過ごせるように病院や産院選びをしましょう。
陣痛タクシーとは陣痛などで出産が始まった時に優先的に配車サービスを受けられる事前登録制度で、「妊婦タクシー」や「マタニティタクシー」などの名称でも知られています。陣痛タクシーは、破水に備えて車内が防水仕様だったり、防水シートを準備したりしており、臨機応変に対応してくれます。
さらに、ドライバーは特別な講習を受けているため、安心して乗車できるようになっています。自家用車で来院予定の場合も、家族が仕事などで送ってもらうことが出来ないタイミングがあるかもしれません。万が一のときに備えて、陣痛タクシーに登録しておくと安心できますね。

妊娠期間中は、出産に関連するものだけでなくベビー用品も用意しておきましょう。急な入院や出産で慌てないためにも、体調と相談しながら妊娠中期には準備を始めるようにしましょう。ここからは、用意しておくと便利なベビー用品を紹介します。
一般的な新生児のサイズは「50~60cm」です。50~60cmサイズは、生まれてすぐから3ヵ月頃まで着用できます。季節の移り変わりも視野に入れ、着回しや重ね着ができるベビー服や肌着を用意しましょう。
ベビー服や肌着は、吐き戻しやおしっこやうんちの汚れなども考えてそれぞれ5枚程度用意があると安心です。家族やパートナーのサポートを受けづらく、一人で育児を行う可能性がある人は、もう少し多めに準備してもよいかもしれません。
室内では、肌着+上に着る洋服の2枚が基本ですが、寒い時は肌着を2枚にしてもよいでしょう。
外出着はロンパース、ドレスオール、ツーウェイオール、カバーオールなどさまざまな種類があります。生地の材質や厚み、保温性や通気性、着脱のしやすさはそれぞれ異なりますので、ベビーショップなどで実際に手に取って選ぶのがおすすめです。また、季節によっては、靴下やレッグウォーマー、おくるみ、帽子などを用意してもよいでしょう。
新生児サイズのおむつは、どのメーカーも体重が5kgまでとなっています。おむつはいろんな種類があるので、どれを使おうかと悩むこともあるでしょう。素材やフィット感、肌へのやさしさ、価格などをみながら選んでみてください。
成長が早い赤ちゃんはあっという間にサイズアウトしてしまうこともあるので、買い過ぎには注意です。その他にも、おしりふきやおむつ用のゴミ箱やゴミ袋も用意しましょう。
母乳だけで育てることを予定している人も、哺乳瓶を1本用意しておくと役に立つことがあります。哺乳瓶は、瓶の素材やサイズ、乳首の素材や形にさまざまなものがあり、赤ちゃんによって好みがあります。あらかじめたくさん準備しておく必要はなく、母乳分泌の状況や赤ちゃんの哺乳具合に応じて購入するようにしましょう。
そのほかにも、ミルクや哺乳瓶用の消毒セット、母乳パッド、授乳ブラなども必要に応じて準備しましょう。搾乳器の購入を検討している方は、出産後に助産師と相談し、必要な場合のみ購入もしくはレンタルを検討するようにしましょう。
赤ちゃんは新陳代謝が活発で汗をかきやすく、うんちやおしっこの回数も多いため、清潔を保つために沐浴(もくよく)をします。沐浴では赤ちゃんを裸にするので、身体を観察するいい機会になります。
生まれてすぐは感染予防のために家族と分けてお風呂に入るため、ベビーバスなどを使用するのがおすすめです。赤ちゃんの肌は刺激に弱いので、ベビー用ソープを使用してください。そのほかに、沐浴用ガーゼや湯温計、沐浴後のスキンケア用品の準備も忘れないようにしましょう。
生後1ヵ月ごろに行われる健診で医師からの許可が出たら、大人と一緒にお風呂に入れるようになります。赤ちゃんをお風呂に入れる方法については、こちらの記事で解説しています。ぜひあわせて参考にしてください。
今回は妊娠期間の平均と数え方、妊娠から出産までの流れと準備しておきたいことについて解説しました。妊娠期間中に妊婦さんの体調も変化し、目に見えないくらい小さかった赤ちゃんが生まれる頃には3㎏程度に大きくなります。体調は妊娠週数や月数の経過とともに変化するため、つらいときには無理をせず、周りの人を頼ることが大切です。
母子手帳の取得や産休・育休の確認、陣痛タクシーの登録など、時期に応じた出産と産後の準備をし、安心して赤ちゃんを迎えられるようにしましょう。
妊婦さんと赤ちゃんのお肌に優しいケア用品をお探しの場合は、ぜひMilpoche Organics(ミルポッシェオーガニクス)の商品をご活用ください。
参考資料
2)母子健康手帳の交付・ 活用の手引き 平成23年度厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)

助産師歴20年以上。総合病院や個人病院などで1,000件以上の分娩の現場を経験した後、 現在は「妊婦さんやママにより寄り添うケアがしたい」という想いから、岡山県にある自身の助産院にて相談や訪問ケアを行う。
カテゴリを選択してください。
カテゴリ
贈る相手
特急便
{{lv1.CategoryName}}